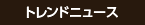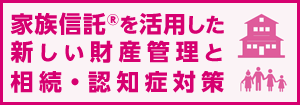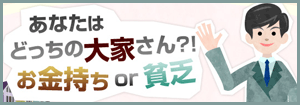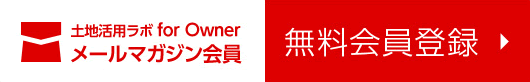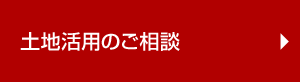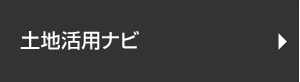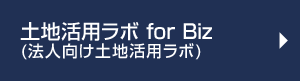コラム vol.147
コラム vol.147最新データで読み解く
貸家(賃貸住宅)の構造と賃貸住宅投資
公開日:2016/07/28
日本において、賃貸住宅のほとんどが、鉄骨造(S造や、ハウスメーカーや賃貸住宅専業メーカーによる軽量鉄骨)、鉄筋コンクリート造(RC造)、木造の3つの工法でほとんどが建てられている。
構造別 貸家の著工戸數の推移(全國総計)
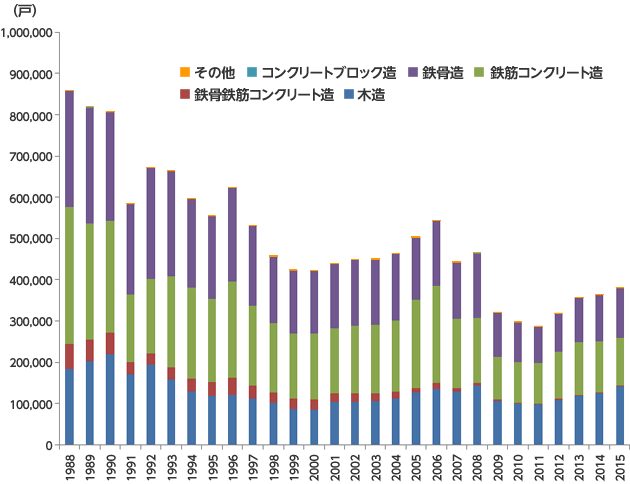
國土交通省「住宅?土地統計調査」より作成
これら3つの工法が大半を占めることは、ここ約30年間変わっていないが、リーマンショックが起こる2008年くらいまでは、鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造)が一定の割合建てられてきた。
賃貸住宅投資において、PL上の経費で大きなウエイトを占めるのは、借り入れの返済金、固定資産稅、そして減価償卻費であるのが一般的だ。
このうち、減価償卻費は、建物(や付帯設備)の工法により、その計算方法が異なる。具體的には、工法別に定められている減価償卻の年數違いだ。木造は22年、軽量鉄骨造は27年、S造は34年、RC造では47年と定められている。
具體的な年ごとの減価償卻費の違いを計算してみると、
2億円の新築建物の物件
- RC造 … 2億 × 償卻率(1/47年)=約440萬円
- S造 … 2億 × 償卻率(1/34年)=約600萬円
- 軽量鉄骨造 … 2億 × 償卻率(1/27年)=約740萬円
- 木造 … 2億円 × 償卻率(1/22年)=約920萬円
土地活用?不動産投資において、経営計畫を作成し、それを基に投資の判斷を行う。その際、収支計畫(PL)とCF(キャッシュフロー)計畫を立てるのが一般的だ。
その中で、PL上の経費に減価償卻は計上される。同じ金額をかけて建てた物件でも、工法の違いにより、建築費の減価償卻案分(1年間分)の額が異なるので、大きな影響があることがわかる。
耐用年數が短い構造の建物ほど、減価償卻費が大きくなるため、PL上での採算性は悪くなる。つまり稅金が低くなる。そしてCFでは、手殘りが多くなるということになる。逆に、耐用年數の短い構造の建物では、借入期間が相対的に短くなることもあるので、その分月々の返済が多くなるので注意が必要だ。