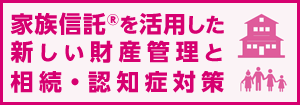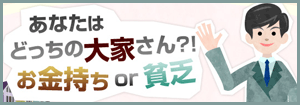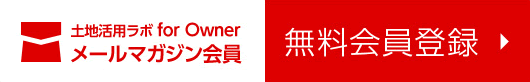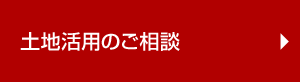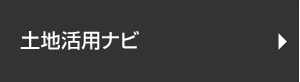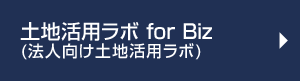コラム vol.327-3
コラム vol.327-3賃貸経営の基本を?qū)Wぼう!法律Q&A第3回 定期借家契約とは?
公開日:2020/06/30
今回は、借地借家法第38條に定められている定期借家契約を取り上げたいと思います。借地借家法による普通借家権については、法定更新の適用があり、この法定更新を拒絶するためには、いわゆる正當(dāng)事由が認(rèn)められなければなりません。そのため、オーナー様から賃貸借契約を終了させることは難しく、普通借家契約を前提にすると、賃貸期間を明確に限定して賃貸することはできないといえますが、定期借家契約では、法定更新のない賃貸借契約を可能としています。
Q1:借地借家法第38條に定める定期借家契約を締結(jié)するためには、公正証書によって締結(jié)しなければなりませんか。
A1:定期借家契約については、借地借家法第38條1項においては、「公正証書による等書面によって締結(jié)するときに限り」認(rèn)められているとされています。そのため、必ず書面で契約書を作成して締結(jié)する必要がありますが、書面の形式としては、必ずしも公正証書による必要はないとされています。なお、いわゆる一般定期借地契約の締結(jié)についても、上記と同様に借地借家法第22條において「公正証書による等書面によってしなければならない」と定められていますが、事業(yè)用定期借地権については、同法第23條では「公正証書によってしなければならない」とされ、事業(yè)用定期借地契約については必ず公正証書によって作成する必要がありますので、注意してください。
Q2:借地借家法第38條に定める定期借家契約を締結(jié)するにおいて、口頭で、契約が更新されずに期間満了により終了することを説明しましたが、書面の交付は省略してしまいました。この場合、定期借家契約としての効力は認(rèn)められるのでしょうか。
A2:定期借家契約については、契約締結(jié)前に、賃借人に対して、契約が更新されず、期間満了により契約が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならないとされています。この事前の説明や書面の交付を怠りますと、定期借家契約として認(rèn)められなくなってしまいます(ただし、借家契約自體が無効となる訳ではなく、契約の更新がないとの特約部分に限り無効となります)。仮に、上記のとおり、定期借家であることの説明を記載した書面を交付しなかったとしても、事前に交付した契約書上に、契約の更新がなされないことが明確に記載してあれば、借地借家法第38條2項に定める説明書面の交付をしたといえる見解もあります。しかし、定期借家か否かは賃借人にとって重要な事項ですから、契約書とは別に説明用の書面を作成し、交付すべきものと考えます。従いまして、定期借契約を締結(jié)する場合には、あらかじめ、必ず契約の更新がないこと等の説明を記載した書面を賃借人に交付する必要があると考えます。なお、オーナー様の仲介をしている宅地建物取引業(yè)者が、「重要事項説明」をした場合でも、上記の事前説明をしたとはいえず、必ず仲介者がオーナー様の代理人として、「重要事項説明」とは別に行わなければならないとされています。
Q3:定期借家契約を締結(jié)するにおいて、賃借人に対して、説明書面を交付し、説明したことを証明するためには、どのような手立てを講じる必要がありますか。
A3:書面による説明義務(wù)は、賃貸人が賃借人に対して定期借家契約であることを十分に理解してもらうために課された義務(wù)になります。ですから、具體的には、契約の更新がないこと、期間の満了により借家関係が確定的に終了すること、契約の終了年月日等を記載した書面を作成し、これを交付のうえ説明し、當(dāng)該書面の受領(lǐng)証を賃借人に作成してもらい、交付を受ける方法が有用です。
Q4:定期借家契約における契約期間は、1年未満の期間であってもかまいませんか。
A4:普通借家契約においては、契約期間を1年未満と合意したとしても、當(dāng)該合意は無効となり、期間の定めのない建物賃貸借契約を締結(jié)したものとみなされます。しかし、定期借家契約においては、1年未満の契約期間も有効とされています。
Q5:定期借家契約においては、再契約を締結(jié)することはできますか。また、再契約を締結(jié)できる場合には、予め自動的に再契約される旨の特約を設(shè)けることも可能なのでしょうか。
A5:定期借家契約に関しては、當(dāng)事者間で別途合意することにより、再度新たに契約を締結(jié)すること(再契約)自體は問題ありません。この場合、事前の書面交付及び説明、書面による契約締結(jié)手続が必要となります。これに対して、例えば、従前の定期借家契約書の契約期間を訂正するだけの変更をした場合には、更新手続がされたとして、普通借家契約とみなされる可能性があり、また、自動的に再契約が締結(jié)されるとの特約が付されているような場合にも、実質(zhì)的に更新を認(rèn)めた契約として、普通定期借家契約が成立していたと解される危険があります。従って、再契約をする場合には、面倒ではありますが、必ず改めて定期借家契約締結(jié)に必要な諸手続を行う必要があります。
Q6:定期借家契約であっても、200m2未満の居住用の建物については、やむを得ない事情により、賃借人において中途解約できるとされていますが、店舗併用住宅の場合であっても、中途解約はできるのでしょうか。
A6:居住の用に供する建物の賃貸借で、床面積が200m2未満の建物に係るものについては、転勤、療養(yǎng)、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができるとされています。この場合、上記床面積の計算は、壁芯面積で判定するとされ、マンションの場合には、共用部分は面積に入れずに、専有部分のみの面積で判定されるとされています。この賃借人からの中途解約権が認(rèn)められているのは、居住用建物に限られているところ、店舗併用住宅であっても、生活の本拠としているものであれば、居住の用に供されている建物であり、中途解約條項の適用対象となります。この場合の床面積の判斷ですが、現(xiàn)に居住用に供している部分の床面積が200m2未満か否かによって判斷するとの見解と、建物全體の床面積が200m2未満か否かで判斷するとの見解がありますが、原則として、後者の見解によるものと考えられています。