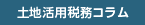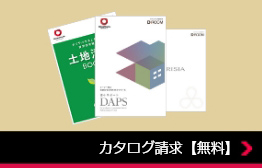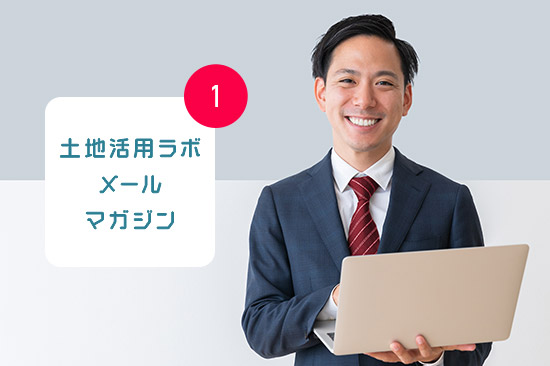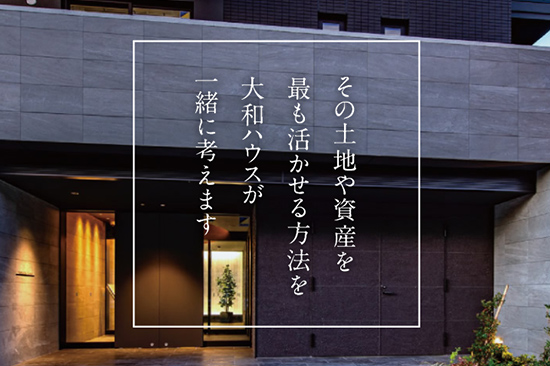コラム vol.515-9
コラム vol.515-9賃貸住宅経営は不動産事業(9)賃貸住宅経営で適正に家賃を設定する
公開日:2025/03/31
賃貸住宅経営を自ら行う場合、重要なポイントが、家賃の問題です。適切な家賃を設定できるかどうかによって、賃貸住宅経営に大きな影響を與えます。賃貸住宅の持つ本來の価値からかけ離れた家賃を設定すれば、ご入居者がいない狀態になりかねませんし、逆に低すぎる家賃では、そもそも収益に問題が出てしまい、経営が成り立ちません。
賃貸住宅経営において、家賃をいくらに設定するかは、収益に大きく影響を與える重大な要素です。昨今、建設會社や不動産管理會社などと一括借上契約を結ぶケースや、管理を全面的に委託している場合を除き、不動産オーナー自ら賃貸住宅を経営、管理する場合、基本的には、オーナーが家賃を決めます。ただし、家賃の交渉は借地借家法という法律において借賃増減請求権という権利として、ご入居者に認められています。
賃貸住宅も商品のひとつなので、原則として需要と供給のバランスで決まりますが、不動産オーナーとして、どのような基準で家賃を決定すればいいのか、整理しておきましょう。
期待利回りから設定する
賃貸住宅経営は基本的に事業ですから、當然収益を出すのが目的です。賃貸住宅経営を行う場合、収支目標として利回りを設定しますので、目指す利回りが決まれば、そこに近づくための家賃収入がどれくらいあれば良いのかを逆算できます。利回りには、単純に受け取る賃料を投資額で割った「表面利回り」と、賃料から諸経費を引いた金額を投資額で割った「実質利回り」があります。
賃貸住宅を取得するためには、必ず諸経費はかかりますので、経営の実態に近い「実質利回り」で計算をすると良いでしょう。
実質利回り(%)=(年間家賃収入-年間経費)÷(賃貸住宅投資価格+取得時の諸経費)×100
不動産の基礎価格に期待利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して、賃料を求める手法を「積算法」と言います。基礎価格とは、基礎となる対象不動産の価格のことで、期待利回りとは、投資金額に対して期待される利益の割合です。この場合の必要諸経費には、維持管理費、固定資産稅?都市計畫稅、火災?地震などの損害保険料、減価償卻費などを含みます。
積算家賃= 基礎価格× 期待利回り+ 必要経費
この方法で求めた家賃は、投資した金額から計算しますので、賃貸住宅オーナーの利益を確保できる賃料を算出することができます。ただし、地域の家賃相場などを考慮していませんので、家賃相場とは乖離してしまうことがあります。
相場に合わせて設定する
ご入居者が賃貸住宅を選ぶ際には、多くの場合、他の賃貸住宅との比較をした上で選びます。その場合、周辺地域の賃貸住宅との競爭となりますので、周辺にある競合になりそうな賃貸住宅の相場家賃を把握し、家賃を設定する必要があります。同じような仕様にもかかわらず、家賃が周辺の賃貸住宅と大きく乖離してしまうと、ご入居者から選ばれにくくなります。
周辺の賃貸住宅やマンションの家賃相場を調べ、比較して賃料を求める方法を「賃貸事例比較法」と呼びます。地域を決めて賃貸住宅を選択するご入居者に対しては、有効な方法と言えるでしょう。
一般的に賃貸住宅やマンションの賃料は、以下の要素によって変動します。
| 立地 | 生活利便性のための、駅などの交通機関や商業施設、公園などとの距離 |
|---|---|
| 築年數 | 美観を備えた上での築年數、部屋の美しさ |
| 階數 | 階數による景観など |
| 設備 | キッチンやバスルームなどの設備、またオートロックや宅配ボックスなど生活利便性や安全性につながる設備、省エネルギーにつながる設備など |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造?鉄骨造?木造などの工法 |
| 管理 | 管理面での利便性 |
當然、ご入居者によって、住まいに対するニーズはさまざまですから、優先順位や選択する基準は変わってきます。そのため、さまざまな要素を考慮した上で、家賃を設定する必要があります。「○○があるから、こういう家賃になった」と明解に説明できれば、ご入居者の判斷もしやすくなるでしょう。
また、特定のニーズに特化した賃貸住宅の場合(たとえば、音楽関係者のために防音施設がある、ペット可能など)は、通常とは異なる周辺ニーズの調査が必要であることは言うまでもありません。
賃貸事例比較法の場合、オーナーの利益を確保できる家賃かどうかは分かりませんので、積算法とセットで検討するのが良いでしょう。すでに、積算法で、利益面から見た家賃を設定している場合は、この相場から見た家賃と比較してみることも大切です。
敷金と禮金も考慮して設定する
入居時に徴収する敷金と禮金も、収益に影響を與えます。どちらも家賃によって金額が変わります。敷金は、入居者に家賃滯納があったときや退去時の原狀回復費用に備え、擔保として預かる資金ですから、預り金ということになります。
一方、禮金は、入居者への返還義務はありませんので賃貸収益の一部となりますが、將來のことを考え、環境の変化によって家賃を下げざるを得ない狀況になったときの資金として確保しておくといった対策をとっておくことも、賃貸住宅経営には必要なことではないでしょうか。
収益と相場のバランスを考え、家賃を設定する
収益を重視するにしても、周辺地域の相場を重視するにしても、雙方から算出した家賃両面から慎重に検討することが重要です。
また、少しでも高い家賃に設定したい場合には、入居者にとって魅力的なメリットを同時に提供することも必要です。入居希望者が集まらなかったり、退去されたりすると、収益性そのものが失われてしまい、本末転倒の結果となってしまいます。ご入居者のニーズに合った賃貸住宅にすることが何よりも大切なことです。